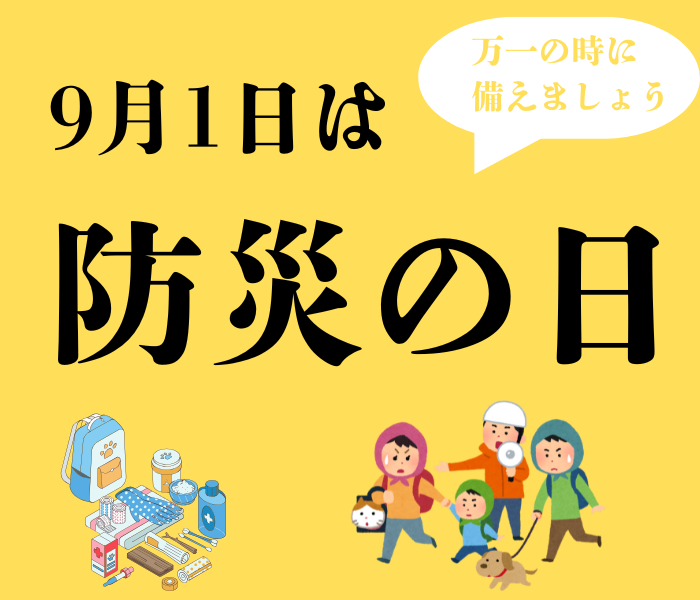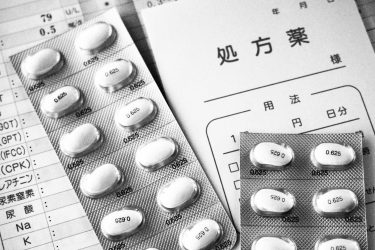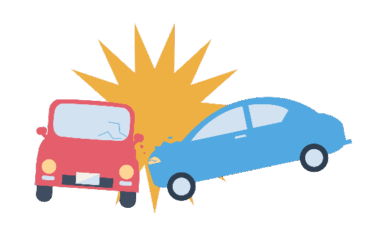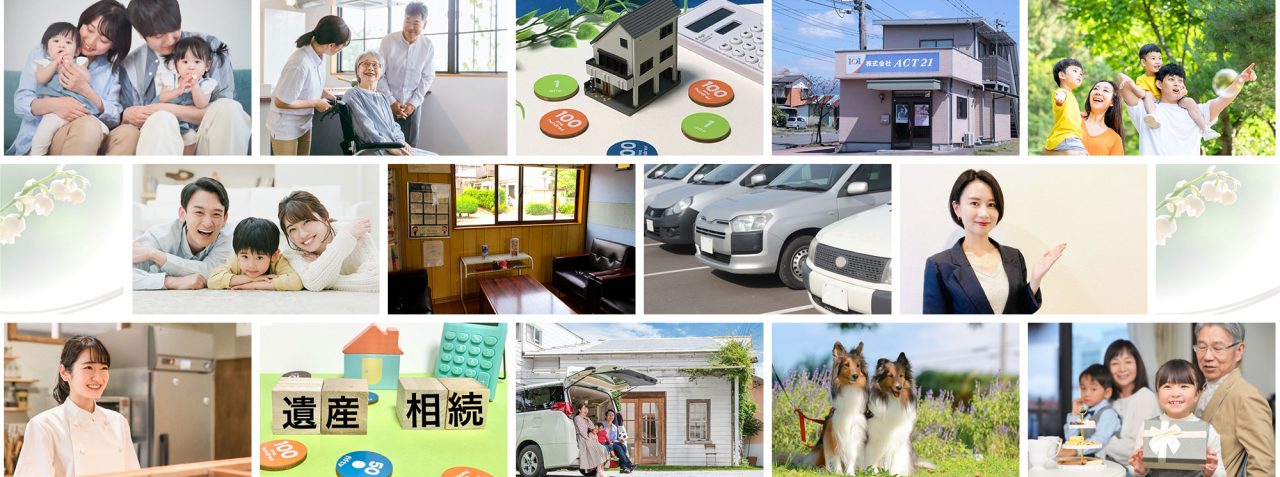災害はいつ、どこで起こるかわかりません。いざという時に大切な家族を守り、生活を再建できるように、日ごろから万全の備えをしておくことが重要です。
小さな備えが、ご家族の大きな安心につながります。今日からできる具体的な対策を確認しましょう。
💧 水と食料の備蓄:最低3日分、目標は1週間分
ライフラインが寸断された場合、支援物資が届くまでには時間がかかります。まずは自力で乗り切るための備蓄が不可欠です。
| 項 目 | 目安 | 備蓄のポイント |
| 飲料水 | 1人あたり1日3リットル × 3日~7日分 | ペットボトルで備蓄。水は重いため、運びやすい場所や分散して保管しましょう。 |
| 食 料 | 1人あたり1日3食 × 3日~7日分 | 火を使わずに食べられる缶詰、レトルト食品、乾パン、栄養補助食品など。 |
【賢く備蓄する「ローリングストック法」】
備蓄品は、「使ったら買い足す」習慣をつけることが重要です。
日常的に食べている食品を少し多めに購入し、賞味期限が近いものから消費し、消費した分だけを買い足す「ローリングストック」を取り入れましょう。これにより、常に新鮮で消費期限にゆとりのある備蓄を維持できます。
🎒 非常持ち出し袋:すぐに持ち出せる「命を守るセット」
災害発生直後に避難する際に必要なものを、リュックサックなどに詰めて、玄関や寝室の近くなど、すぐに持ち出せる場所に保管しておきましょう。
| カテゴリ | 必須アイテムの例 | 詳しく備えたいこと |
| 情報・通信 | 懐中電灯、携帯ラジオ(手回し充電式)、モバイルバッテリー、予備電池、ホイッスル | 停電時でも情報収集ができるよう、手回し充電機能付きのものがおすすめです。 |
| 衛生・医療 | 常備薬(かかりつけ医の連絡先も)、マスク、除菌シート、救急セット(絆創膏、消毒液など)、簡易トイレ | 薬は数日分を確保し、お薬手帳のコピーも一緒に入れておきましょう。 |
| 貴重品 | 現金(小銭も)、身分証明書・保険証のコピー、通帳のコピー、印鑑 | 避難先で利用できるよう、小銭(公衆電話や自動販売機用)も用意しておきましょう。 |
| その他 | 防寒具(ブランケット)、軍手、タオル、ポリ袋(大小)、レインコート | ポリ袋は、防寒や簡易的な水入れなど、多用途に使えます。 |
📞 家族との連絡方法の共有:安否確認のルールを決めておく
災害時は電話回線が混み合い、連絡が取りづらくなることが想定されます。家族間で事前にルールを決めておくことが、安否確認の鍵となります。
- 災害用伝言ダイヤル(171): NTTが提供するサービス。音声による伝言を残したり、再生したりできます。
- 災害用伝言板(Web171): インターネットを通じて、安否情報(テキスト)を確認・登録できます。
- SNSの活用: LINEやX(旧Twitter)などのSNSは、電話回線よりもつながりやすい場合があります。事前に家族グループを作成し、安否確認のメッセージを送るなどのルールを決めておきましょう。
- 集合場所: 災害の種類や状況によって、自宅に戻れない場合を想定し、一時的な避難場所と、より安全な広域避難場所の2か所を決めておきましょう。
🔩 家具の転倒防止対策:ケガの予防と避難経路の確保
地震が発生した際、負傷の原因の約$30%~50%$は、家具の転倒・落下・移動によるものと言われています。
• 突っ張り棒・固定金具の活用: タンスや食器棚など、背の高い家具は必ず突っ張り棒やL字金具で壁や天井にしっかりと固定しましょう。
• 寝室の安全確保: 就寝中に家具が倒れてこないよう、ベッドの周りには背の高い家具を置かないようにし、避難経路を確保しておきましょう。
• ガラス飛散防止: 窓ガラスや食器棚のガラスには飛散防止フィルムを貼っておくことで、割れたガラスによるケガを防ぎます。
🤝 保険代理店からのメッセージ:災害時の「もしも」に備える
防災対策は、身体的な安全を守るだけでなく、「生活の再建」という観点も重要です。
- 火災保険の確認: 地震による火災・損壊・津波の被害は、一般的な火災保険だけでは補償されません。「地震保険」に加入しているか、補償内容は十分か、今一度ご確認ください。
- 生命保険・医療保険の確認: 災害によりケガや病気を負った場合の治療費や、万が一の際の生活費について、保険で備えができているか確認しましょう。
当社の専門家が、お客様の地域のリスクを考慮した上で、「もしも」の時の備えと「生活再建の費用」について最適なプランをご提案いたします。
💡 今すぐできる具体的なアクション
- 自宅の非常持ち出し袋を点検し、中身と賞味期限を確認する。
- 家族会議を開き、災害時の連絡方法と集合場所を再確認する。
- ハザードマップを確認し、自宅周辺の避難経路を確認する。
今日から少しずつ防災準備を進めて、ご家族の未来の安心を守りましょう。